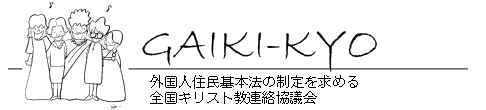今年も8月からスタートしている「外国人住民基本法の制定を求める全国リレー集会2025」。各地の集会の報告が届いています。(2025年10月15日更新)
各地外キ連・各教派団体の集会報告2025
●8月9日●
◇講師:師岡康子さん(弁護士/外国人人権法連絡会事務局長)
◇テーマ:クルドヘイトの現状と闘い――社会が抱える問題としてのヘイト 川口・蕨
◇会場:大宮バプテスト教会
◇主催:日本バプテスト連盟 北関東地方連合社会委員会/日韓・在日連帯特別委員会
◇共催:外キ協/神奈川外キ連/関東外キ連
◇会場参加:15名/オンライン参加50人(7教派団体)
本集会は、例年行なっている日本バプテスト連盟北関東地区8・15平和集会の枠を用いて、外キ協、神奈川外キ連、関東外キ連の協力のもと開催されました。戦後80年、この国は戦争こそないものの、差別と排除の根は深く、平和とはいえない状況です。私が住む埼玉県でも川口市、蕨市周辺ではクルドの方がたへのヘイトスピーチが蔓延しています。これはクルド人の問題ではなく、日本社会の問題であることから、クルドヘイト対策弁護団でもある師岡康子弁護士の話を聞きました。
日本に暮らすトルコ国籍者数は7,571人(2024年6月末現在)、うち埼玉県内は全国最多の2,441人、在留資格のない非正規滞在者約900人を合わせると、県内には約3,300人が暮らしており、その大半がクルド人です。埼玉県川口市では、1993年川口に居住し、解体業で働いて独立したある方を中心にクルド人住民が増えました。と言っても川口市全人口約60万人(2025年1月1日現在)のうち、トルコ国籍者はわずか0.2%(およそ2000人)です。
師岡さんは、そのような少数のクルドの方がたが、2023年頃からヘイトの標的とされるに至った要因として「公権力による偏見の助長」を挙げました。2023年6月29日、川口市議会がクルド人を問題視して出した「一部外国人による犯罪の取り締まり強化を求める意見書」は、クルドの方がたに対する偏見を助長する公的根拠の一つとされました。確かにクルドの方がたの中に犯罪を犯した人もいます。しかし、それは日本人で犯罪を犯す人がいるのと同様であり、日本人の犯罪率のほうが圧倒的に高いことから考えても、これは公権力による偏見と言わざるを得ません。このような公的ヘイトは県議会議員、国会議員をはじめ、参院選でも公然となされましたが、それらは決して許してはならないものであることを確認しました。
また、ヘイトスピーチを止めるためには国レベルでの人種差別撤廃法制定の他、川崎市をモデルとする反差別条例が各自治体レベルでも必要であることを再認識しました。また、一部報道機関やネットによる偏見の扇動されることなく、事実に基づき、事実を伝えていくような市民レベルの活動も求められていることを受け、積極的平和をつくりだす者として地域や教会で出来ることは何であるか、と問われた集会でした。
●永松 博(日本バプテスト連盟 大宮バプテスト教会牧師)
●8月18日●
外キ協全国リレー集会in函館/北海道外キ連夏期キャラバン
◇講演①:林 炳 澤さん(自由学校「遊」共同代表)
「在日韓国人から見た、2023~24年の〝入管法改悪”を問う」
◇講演②:森谷康文さん(北海道教育大学准教授)
「日本の『多文化共生』がすすまないのはなぜか」
◇会場:カトリック湯川教会
◇主催:北海道外キ連
「共に生きてる仲間たち」をテーマにした集会がカトリック湯川教会で開催され、会場に28名、Zoomを合わせて約50名が参加しました。会場を提供くださったカトリック湯川教会の皆様に心より感謝申し上げます。
前半の講演では林炳澤さんが、「日本人ファースト」というスローガンに触れ、日本の社会構造そのものが日本人ファーストであることを指摘。参加者は、日本社会が内包する排他的な構造と自身のマジョリティ性に改めて気づかされました。続く森谷康文さんの講演では、政府主導の多文化共生が進む中でも「マジョリティに役に立つか」という価値観が優先される現状が浮き彫りにされました。異文化交流を表面的なものに留めず、「平等とは何か」を深く問いかける交流の重要性が強調されました。
翌日19日には、函館周辺の碑石巡りが行われ、戦時捕虜を追悼する永全寺を訪問。「Peace and Reconciliation(平和と和解)」と刻まれた祈念塔を前に、私たちが真に目指すべき多文化共生と和解のあり方に思いを馳せる貴重な機会となりました。
●西本詩生(北海道外キ連/札幌バプテスト教会牧師)